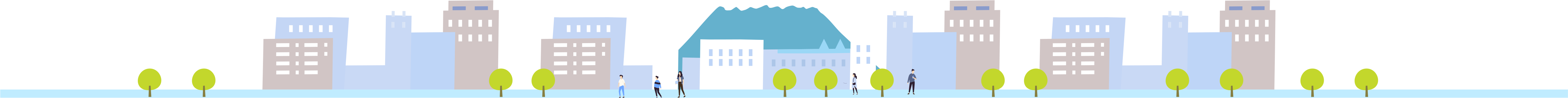口の中には、味を感じる取る細胞「味蕾」があります。およそ5千~1万個ほどで、多くは舌の表面に存在します。幼児期には頬や下の裏側にも分布していますが、加齢とともに数が減少し、高齢者は若年者の3分の1程度になるといわれています。
味蕾が減ると甘み、塩味、酸味、苦みの順に感じにくくなり、「口の中が酸っぱい」「苦く感じる」といった違和感が生じます。これが味覚障害です。原因はさまざまですが、特に多いのが「亜鉛欠乏性味覚障害」です。味蕾の細胞は約10日周期で生まれ変わるといわれ、その過程に亜鉛とビタミンCが欠かせません。亜鉛は成人で一日約15ミリグラムの摂取が目安とされ、ビタミンCは亜鉛の吸収を助けます。
このほかにも、喫煙や薬の副作用、ストレス、唾液の分泌低下などが味覚に影響を及ぼすことがあります。精神的なストレスが続くと自律神経の働きが乱れ、味覚が鈍くなることもあります。さらに、唾液の出が悪く口の中が乾燥する状態(ドライマウス)では、味物質が味蕾まで届きにくくなり、味を感じにくくなります。加齢や薬の影響、糖尿病、シェーグレン症候群などが唾液分泌低下の原因となることもあります。
味覚障害の患者は、女性が約3分の2を占め、50代以降から増加します。味蕾の減少に加え、ホルモンの影響も関係していると考えられます。
亜鉛不足が原因の場合、改善は早ければ数週間から1ヶ月ほどで見られますが、再発を防ぐためには3~6ヵ月間の継続的な栄養補給が望まれます。亜鉛を多く含む食品には、カキ、カツオの塩辛、サバ節、煮干しなどがあります。日々の食事で、これらを意識的に取り入れてみましょう。
(鹿児島県歯科医師会 理事 湯田 晃大)
原因の多くは亜鉛不足 味覚障害